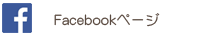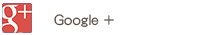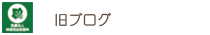「性教育」という言葉を聞いたとき、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか? 単に体の仕組みを学ぶこと、あるいは少し恥ずかしい話題だと感じるかもしれません。
しかし、性教育は、私たちが心身ともに健康で、互いを尊重し合える社会を築くための根幹となる教育です。
本記事では、泌尿器科専門医の視点から、性教育の基本的な考え方から、日本における現状と課題、そして男女の体の違い、性の健康に関する重要な知識までを幅広く解説します。
正しい知識を身につけ、自分自身と大切な人の未来を守るために、一緒に学んでいきましょう。
札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など
神楽岡泌尿器科では、院長直通の無料メール相談も承っています。尿路結石に対して不安や悩みがある場合は、お気軽にご連絡ください。
性教育とは?基本的な考え方
性教育とは、「人間と性」に関するあらゆる側面を学ぶ教育です。
古来より、人類社会では性交、妊娠、出産、避妊などに関する知識が世代を超えて伝えられてきました。これが、性教育の原初的な形態と言えるでしょう。
近代国家が成立すると、健康な国民は労働力や兵力といった「国力」の基盤と位置づけられ、人口増加が重視されました。
そのため、婚姻制度の中で生殖に貢献する異性愛規範を持つ道徳的な国民を育成することが求められ、その手段の一つとして学校における性に関する教育が重要視されるようになったのです。
その後、国家の要求に加え、多様な思想を持つ市民が性教育に対する要望を掲げ、教育内容を提起してきました。
その結果、現代の「性教育」は、身体的な知識だけでなく、心の健康、人間関係、ジェンダー、自己決定、権利、多様性、安全など、多岐にわたる内容を含むようになっています。
福永玄弥氏の研究によれば、東アジアでは「純潔教育」「道徳教育」「性教育」「人権教育」「包括的セクシュアリティ教育」「男女平等教育」「ジェンダー教育」「ジェンダー平等教育」など、様々な枠組みに基づいて多様な「性教育」が実施されてきました。この多様性は、「性教育」のあり方が固定的なものではなく、社会の変化に応じて常に変化していることを示唆しています。
(参考:日本大百科全書(ニッポニカ)「性教育」)
日本における性教育の現状と課題
日本では第二次世界大戦後、性教育の刷新と近代化が進みました。
①戦後の日本における性教育
日本では1960年代から1970年代にかけて、性に関する研究が活発化し、海外の知見が紹介される中で、「純潔教育」という言葉への批判が高まり、「性教育」という用語が一般化します。1972年には日本性教育協会が設立されました。
文部省は当初、「純潔教育と性教育は同義語である」という立場を取りましたが、1970年代後半には「性に関する指導」という用語に切り替えます。
1987年に日本で初の女性エイズ患者が確認されたことを契機に、性感染症の増加や若年層の性行動の活発化などを背景に、学校における性教育を求める声が高まりました。
1990年代初頭、男女共同参画の動きがある一方で、日本の戦争責任検証に対する攻撃が激化しました。その流れの中で、性教育とジェンダー平等教育に対しても「過激性教育」とする批判が起こります。
特に2003年の七生養護学校へのバッシングは、性教育の実践に大きな負の影響を与えました。
同校の性教育実践が一部都議会議員によって非難され、東京都教育委員会が教材を回収するなどの事態が発生し、教員が処分されました。裁判では教員らが勝訴しましたが、この事件は性教育の実践に萎縮と後退をもたらしました。
②日本の性教育の現状と課題
日本の学校における性教育は、量と質ともに十分とは言えません。調査によると、中学校3年間での性教育の授業時間は平均8.62時間、1年間では3時間にも満たないのが現状です。
また、教えられている内容も「身体」「妊娠」「性感染症」「月経」「射精」などが中心で、「避妊」「自慰」などは十分に扱われていません。
性教育の不足は、大人も子どもも包括的で科学的な性の知識を得る機会を奪い、インターネット上の不正確な情報に晒される現状を生んでいます。
今後は、国際的なガイダンスに学び、日本の現状を踏まえた包括的性教育プログラムを開発し、全ての学校で実践できる体制を整備すること、若者が気軽に相談できるユースクリニックのような施設を整備すること、インターネット上の正確な情報へのアクセスを向上させるための取り組みなどが求められています。
男性器と女性器について
ここからは、生物学的な観点から、あらためて男性と女性の違いについてみていきましょう。性教育の第一歩は、「お互いの違いを認める」ことから始まるからです。体のつくりが異なるように、生殖の役割を担う器官の構造も大きく異なります。
①男性生殖器
| 精巣(睾丸) | 陰嚢内に左右一対存在し、精子と男性ホルモン(テストステロン)を産生します。 |
| 精路 | 精巣で生成された精子が通過する経路の総称です。 |
| 精管 | 精路の一部であり、精巣から精子を輸送する管です。 |
| 精嚢 | 精管の途中に位置し、精子の運動能力を助ける液体(精液の一部)を分泌します。 |
| 前立腺 | 膀胱直下に存在し、精液の構成成分を産生します。 |
| 尿道 | 膀胱からの尿と、精液を体外へ排出する共通の管です。 |
| 陰茎 | 外性器であり、勃起によって精液を女性の生殖器内に送達する機能を持ちます。 |
②女性生殖器
| 卵巣 | 左右に一つずつ存在し、卵子と女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)を産生します。 |
| 卵管 | 卵巣から放出された卵子を子宮へ輸送する管であり、受精は主にこの部位で行われます。 |
| 子宮 | 妊娠時に胎児が発育する袋状の器官です。内壁は受精卵の着床に適した状態に周期的に変化します。 |
| 子宮頸部 | 子宮の出口であり、膣と連続しています。 |
| 膣 | 外性器から子宮へと続く管であり、性交時には男性の陰茎を受け入れ、出産時には産道となります。 |
| 外陰部 | 女性の外性器全体の名称であり、大陰唇、小陰唇、陰核(クリトリス)などで構成されます。 |
③月経(生理)について
月経(生理)とは、女性ホルモンの周期的な変動により、子宮内膜が剥離・出血する生理現象です。一般的に25~38日周期で反復し、出血期間は3~7日程度です。
月経前には、ホルモンバランスの変化に起因するPMS(月経前症候群)として、精神的な不安定や身体的な不調が現れることがあります。
▶月経との適切な向き合い方:
| 生理用品の適切な使用 | ご自身に適した生理用品を選択し、衛生的に使用することが重要です。 |
| 体調管理 | 無理を避け、体を温めたり、十分な休息をとるように心がけましょう。 |
| 専門家への相談 | 月経痛が著しいなど、困った症状がある場合は、遠慮なく医療機関に相談してください。 |
▶月経痛や月経不順、それは見過ごせないサインかもしれません:
「生理痛は毎月のことだから」「生理周期が少し乱れるのはよくあること」と、特に気にせず放置していませんか?
確かに、月経痛や月経不順は多くの女性が経験する症状です。しかし、その裏には、子宮内膜症、子宮腺筋症、子宮筋腫、多嚢胞性卵巣症候群といった病気が隠れている可能性があることを知っておいてください。
これらの病気は、放置することで症状が悪化したり、不妊の原因になったりすることもあります。
「よくあることだから」と安易に考えず、もしあなたが以下のような気になる症状を感じているのであれば、ためらわずに産婦人科医に相談してみましょう。
- これまでよりもひどくなった生理痛
- 市販の鎮痛薬が効かないほどの痛み
- 生理時以外の下腹部痛や腰痛
- 生理周期が極端に短い、または長い
- 生理がなかなか来ない、または頻繁に来る
- 生理の出血量が明らかに増えた、または減った
- 生理期間が異常に長い、または短い
- 生理ではない時期の出血(不正出血)
あなたの「いつもと違う」と感じるサインは、体がSOSを出しているのかもしれません。早期の相談と適切な診断によって、病気の早期発見や進行の抑制につながることがあります。ご自身の体の声に耳を傾け、気になることがあれば専門医に相談することが大切です。
性の健康
性の健康とは、単に性関連の疾患がない状態を指すのではなく、身体的、精神的、社会的に良好な状態を包括する概念です。ご自身と大切な人の性の健康を守るために、以下の点を理解しておきましょう。
①性感染症(STI)の予防
性感染症とは、 性行為によって病原体が伝播する感染症の総称です。
クラミジア感染症、淋菌感染症、梅毒、HIV感染症など、多様な種類が存在します。無症状の場合もありますが、放置すると不妊症や重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
▶予防の基本:
| コンドームの適切な使用 | 性交渉の開始から終了まで、正しくコンドームを使用することで、多くの性感染症のリスクを低減できます。 |
| パートナーとのコミュニケーション | お互いの性に関する健康状態について開かれた対話を持つことが重要です。 |
| 定期的な検査 | 不安を感じる場合は、医療機関で性感染症の検査を受けることが可能です。匿名での検査が可能な機関もあります。 |
②意図しない妊娠の予防
女性の卵巣から排卵された卵子と、男性の精子が卵管内で受精することで妊娠が成立します。
意図しない妊娠を避けるためには、適切な避妊方法に関する知識が不可欠です。
▶予防の基本:
| コンドーム | 性感染症の予防と同時に避妊効果も期待できます。 |
| 経口避妊薬(ピル) | 女性が継続的に服用することで排卵を抑制し、高い避妊効果が得られます(医師の処方が必要です)。 |
| 緊急避妊薬(アフターピル) | 避妊に失敗した場合や、予期せぬ性交渉があった際に、一定時間内に服用することで妊娠を阻止できる可能性があります(医師の処方が必要です)。 |
避妊は一方的な責任ではなく、パートナーと協力して取り組むべき課題です。
③思春期の身体的変化と精神的な成長
思春期には、性ホルモンの分泌が活発になり、男性では声変わり、体毛の増加、筋肉量の増加などが、女性では乳房の発達、月経の開始など、身体に様々な変化が生じます。いわゆる第二次性徴です。これらは、成熟した大人へと成長するための自然な過程です。
身体の変化に伴い、異性への関心が高まったり、自身の性について深く考えるようになります。
変化する自身の身体を受け入れ、大切にしましょう。 身体的な成長には個人差があります。焦らず、自身のペースを尊重しましょう。
困難に直面した際は、信頼できる大人(家族、教員、スクールカウンセラーなど)に相談することで、心理的な負担が軽減されることがあります。
④性行為と他者の尊重
性行為は、二人の間に親密な感情や喜びをもたらす特別な行為です。しかし、その根底には、相手への深い尊重の気持ちが不可欠です。
▶まずは同意から:
相手を尊重することは、単にルールを守るということではなく、相手の心と体の両方を大切に思い、その意向を尊重することに繋がります。
尊重の第一歩は「同意(Consent)」です。 性行為は、お互いが心から「したい」と思い、明確に同意している場合にのみ成立します。どちらか一方でも嫌がっていたり、不安を感じていたりする場合は、絶対に行うべきではありません。
同意は一度得たら終わりではなく、行為の途中でも確認し合うことが大切です。もし、相手が少しでも躊躇したり、嫌がる素振りを見せたりした場合は、すぐにやめる勇気を持つことが、真の尊重の表れと言えるでしょう。
▶相手の価値観を理解する:
自分の価値観を一方的に押し付けるのではなく、相手の気持ちに寄り添い、対話を通じてお互いを理解しようとすることが、健全な関係を築く上で欠かせません。相手の性的指向や性自認、過去の経験なども含め、相手のプライバシーに関わることには十分に配慮しましょう。
性行為は、単なる身体的な接触以上のものです。 そこには、感情や愛情、信頼といった心の繋がりが深く関わっています。相手の体を大切に扱うことはもちろん、相手の心も傷つけないように、言動には常に注意を払いましょう。相手を軽蔑するような言葉を使ったり、一方的な要求をしたりすることは、相手の尊厳を深く傷つける行為です。
▶「NO」といえる関係の構築:
また、相手の「NO」を尊重することは、自己中心的な欲求をコントロールする成熟さを示すものです。 どんなに親しい関係であっても、相手には「したくない」と意思表示をする権利があります。その意思表示を真摯に受け止め、尊重することが、二人の関係をより深めるための信頼へと繋がります。
性に関するよくある誤解と正しい知識
性に関する情報は、様々な場所で飛び交っていますが、中には誤った情報も少なくありません。誤解に基づいた行動は、意図しない妊娠や性感染症のリスクを高める可能性があります。ここでは、性に関するよくある誤解と、医学的に正しい知識を解説します。
「避妊しなくても大丈夫」は本当?
「たまたま一回だけだから」「若いから大丈夫」「相手を信じているから」といった理由で、避妊をせずに性行為に及ぶのは非常に危険な行為です。
避妊しなくても大丈夫」という考えは、全くの誤りです。意図しない妊娠や性感染症のリスクを避けるためには、性行為の際には必ず適切な避妊法(コンドーム、低用量ピルなど)を用いることが重要です。 パートナーとしっかりと話し合い、責任ある行動を心がけましょう。
誤解①: 避妊をしなくても、絶対に妊娠するわけではないから大丈夫。
正しい知識: 妊娠は、たった一度の性行為でも起こりうる可能性があります。排卵のタイミングは予測が難しく、精子は女性の体内で数日間生存することができます。そのため、「たまたま」「一回だけ」という油断は禁物です。
誤解②: 若いから妊娠しにくい。
正しい知識: 若い世代であっても、妊娠する可能性は十分にあります。むしろ、性行為の経験が浅いほど、避妊の知識や実践が不十分な場合があり、意図しない妊娠のリスクが高まる傾向があります。
誤解③: 相手を信じているから、避妊は必要ない。
正しい知識: 避妊は、お互いを信頼しているかどうかとは別の問題です。意図しない妊娠を防ぐための責任ある行動であり、相手への思いやりでもあります。また、性感染症の予防には、コンドームの適切な使用が不可欠であり、信頼関係だけで防ぐことはできません。
「マスターベーションは体に悪い?」医学的な見解
マスターベーション(自慰)は、多くの人が経験する自然な生理現象の一つです。「マスターベーションは体に悪い」という考えは、科学的な根拠のない誤解です。
自身の心身の状態を理解し、適切な範囲で行うマスターベーションは、健康な性を育む上で自然な行為と言えるでしょう。
誤解①: マスターベーションをすると、体が弱くなる、学力が低下する、将来不妊になる。
正しい知識: 医学的に見て、マスターベーションが直接的に体に悪い影響を与えるという科学的な根拠はありません。むしろ、適度なマスターベーションは、性的欲求の解消、ストレス軽減、睡眠の質の向上など、心身の健康にプラスの効果をもたらす可能性も指摘されています。
誤解②: マスターベーションは異常な行為である。
正しい知識: マスターベーションは、思春期以降の男女問わず、多くの人が経験する普通の行為です。特定の年齢層や状況に限ったものではなく、性的発達の過程における健全な表現の一つと考えられています。
誤解③: マスターベーションの頻度が多いと問題がある。
正しい知識: マスターベーションの頻度に「正常」や「異常」といった明確な基準はありません。個人の性的欲求や生活状況によって大きく異なります。ただし、マスターベーションが日常生活に支障をきたすほど過度になる場合(例えば、仕事や学業に集中できない、人間関係に影響が出るなど)は、心理的な問題を抱えている可能性も考慮されます。
若い世代に伝えたい、性と心の健康
私たちは成長する中で、体だけでなく心も大きく変化していきます。
特に、性に関する感情や疑問は、誰にでも起こりうる自然なことです。しかし、情報が溢れる現代において、正しい知識と心の健康を保つことは、時に難しく感じるかもしれません。
ここでは、若い世代が抱きやすい性の悩みについて、大切な視点と相談できる場所をご紹介します。
①ポルノとリアルの違い—誤解を防ぐために
インターネットやメディアで手軽にアクセスできるポルノグラフィー(以下、ポルノ)は、性に対するイメージを形成する上で大きな影響力を持つことがあります。
しかし、ポルノに描かれている世界は、現実の性行為や人間関係とは大きく異なる場合があることを理解しておく必要があります。
ポルノは、エンターテイメントとして作られたものであり、現実の性行為を忠実に再現しているわけではありません。
誇張された表現や、特定の性的行為に焦点が当てられていることが多く、多様な性行為や感情のあり方を反映しているとは限りません。現実の性行為は、もっと穏やかであったり、時間をかけて親密さを深めたりするものです。
現実の健全な性的関係は、お互いの気持ちを尊重し、コミュニケーションを取りながら築き上げていくものです。同意のない性行為は、性的暴力であり、決して許されるものではありません。
ポルノはあくまでエンターテイメントとして捉え、現実の性や人間関係と混同しないように意識することが大切です。現実の世界では、相手への尊重、コミュニケーション、同意が何よりも重要であることを忘れないでください。
②性の悩みを相談できる場所
性に関する悩みは、誰かに相談することで気持ちが楽になったり、解決の糸口が見つかったりすることがあります。一人で抱え込まず、安心して相談できる場所を知っておきましょう。
1. 学校の先生や養護教諭
学校には、皆さんの成長をサポートしてくれる先生や、体のこと、心の健康について相談できる養護教諭がいます。信頼できる先生がいれば、勇気を出して話してみてください。
2. スクールカウンセラー
多くの学校には、専門のスクールカウンセラーが配置されています。性に関する悩みだけでなく、人間関係や将来のことなど、様々な悩みを安心して相談することができます。
3. 地域の相談窓口
各自治体には、青少年向けの相談窓口や、女性のための相談窓口などが設置されている場合があります。電話やメール、面談など、様々な方法で相談することができます。お住まいの地域の情報を調べてみましょう。
4. 医療機関(婦人科、泌尿器科、精神科など)
体のことや心のことで専門的なサポートが必要な場合は、医療機関を受診することも考えてみましょう。婦人科では月経や避妊、性感染症など、泌尿器科では男性の性に関する悩み、精神科や心療内科では心の健康に関する相談ができます。
5. 性教育に関するNPOや支援団体
インターネット上には、性教育に関する正しい情報を提供したり、相談を受け付けたりしているNPOや支援団体があります。匿名で相談できる窓口もありますので、活用してみるのも良いでしょう。
6. 信頼できる大人(家族、親戚など)
もし、安心して話せる家族や親戚がいれば、勇気を出して相談してみるのも良いでしょう。身近な人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
泌尿器科でできる性の健康相談と治療
泌尿器科は、男性の尿路・生殖器系の病気を専門とする診療科ですが、性の健康に関する様々な相談や治療も行っています。ここでは、泌尿器科で相談できる内容と、特に若い世代にとって知っておきたい情報をご紹介します。
神楽岡泌尿器科では、院長直通の無料メール相談も承っています。性のことで不安や悩みがある場合は、お気軽にご連絡ください。
①勃起不全(ED)や早漏・遅漏の悩み
性行為における男性の悩みとして、勃起不全(ED)や早漏、遅漏などが挙げられます。これらの症状は、単に性行為がうまくいかないだけでなく、自信の喪失やパートナーとの関係悪化につながることもあります。泌尿器科では、これらの悩みに対して専門的な相談と治療を提供しています。
▶勃起不全(ED):
十分な勃起が得られない、または維持できない状態です。原因は、加齢による血管や神経の機能低下、生活習慣病(糖尿病、高血圧など)、ストレス、心理的な要因など多岐にわたります。
泌尿器科では、問診や検査を通じて原因を特定し、内服薬、注射薬、陰圧吸引器などの薬物療法や、生活習慣の改善指導、カウンセリングなど、患者さん一人ひとりに合わせた治療法を提案します。若い世代でも、ストレスや生活習慣の乱れからEDになるケースがありますので、悩まずに相談してください。
▶早漏:
意図したよりも早く射精してしまう状態です。原因は、神経の過敏性、心理的な要因、性行為の経験不足などが考えられます。泌尿器科では、内服薬、外用薬、行動療法などの治療法を用いて、射精までの時間をコントロールできるようサポートします。
▶遅漏:
射精までに時間がかかりすぎる、または射精できない状態です。原因は、神経系の異常、薬の副作用、心理的な要因などが考えられます。泌尿器科では、原因を特定するための検査を行い、必要に応じて薬物療法や専門機関への紹介を行います。
これらの悩みは、恥ずかしいと感じて一人で抱え込んでしまうことが多いですが、泌尿器科医は専門的な知識と経験を持っており、プライバシーにも配慮した上で親身に相談に乗ってくれます。悩んでいる方は、勇気を出して泌尿器科を受診してみてください。
②月経やホルモンバランスの影響と性の健康
泌尿器科は主に男性の診療科ですが、パートナーである女性の性の健康に関する相談を受けることもあります。特に、月経やホルモンバランスの変動は、女性の性的欲求や性交痛などに影響を与えることがあります。
▶月経周期と性的欲求
女性ホルモンの変動によって、月経周期の中で性的欲求が高まる時期とそうでない時期があります。パートナーがお互いの体のリズムを理解し、コミュニケーションを取ることで、より良い性生活を送ることができます。
泌尿器科医は、必要に応じて婦人科医と連携し、ホルモンバランスに関する情報提供やアドバイスを行うことがあります。
▶ホルモンバランスの乱れと性交痛:
ホルモンバランスの乱れは、膣の乾燥を引き起こし、性交痛の原因となることがあります。泌尿器科医(特に性機能専門の医師)は、このような症状に対する相談や、潤滑剤の使用などのアドバイスを行うことがあります。より専門的な治療が必要な場合は、婦人科への紹介を行います。
泌尿器科を受診する男性が、パートナーの性の健康について相談することも歓迎されます。カップルで協力して、お互いの性の健康を理解し、より良い関係を築くことが大切です。
③若者向けの性教育外来とは?
近年、若い世代が抱える性に関する悩みは多様化しており、性感染症の予防、避妊、性的指向・性自認に関する疑問、性暴力被害など、様々な相談が増えています。このようなニーズに応えるため、一部の医療機関では「若者向けの性教育外来」を開設しています。
性教育外来で相談できることは、以下の通りです。
▶性感染症(STI)の予防と検査:
正しい予防法や、感染が疑われる場合の検査について相談できます。匿名での検査が可能な場合もあります。
▶避妊に関する相談:
様々な避妊法(コンドーム、ピルなど)のメリット・デメリットについて詳しく説明を受け、自分に合った方法を選ぶことができます。緊急避妊に関する相談も可能です。
▶性的指向・性自認に関する悩み:
誰にも相談できずに悩んでいることについて、安心して話せる場を提供します。必要に応じて、専門の医療機関や支援団体を紹介してもらうこともできます。
▶性暴力被害に関する相談:
辛い経験について相談し、必要な医療的・心理的なサポートを受けることができます。
性教育外来は、若い世代が性の健康に関する正しい知識を身につけ、安心して相談できる場所を提供することを目的としています。
もし、一人で悩んでいることや、誰かに相談したいことがある場合は、性教育外来の利用を検討してみてください。泌尿器科医をはじめとする医療従事者が、皆さんの性の健康をサポートします。
まとめ
本記事では、泌尿器科専門医の監修のもと、性教育の基本的な考え方、日本における現状と課題、男女の生殖器の構造、月経の基礎知識、そして性の健康における重要な側面について解説しました。
性教育は、単なる知識の伝達に留まらず、私たちが心身ともに健康で、互いを尊重し、責任ある行動をとるための基盤となるものです。
もし、性に関する悩みや不安を抱えている場合は、決して一人で悩まず、学校の先生、養護教諭、スクールカウンセラー、地域の相談窓口、医療機関など、様々な相談先があることを覚えておいてください。
特に泌尿器科では、男性の性の健康に関する専門的な相談や治療を提供しています。また、若者向けの性教育外来を開設している医療機関もありますので、積極的に活用してください。

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」
札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など